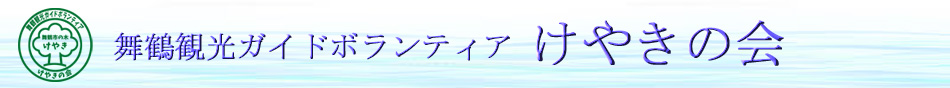舞鶴の歳時記
3月

舞鶴自然文化園ツバキまつり
(3月中旬~4月中旬)
約1500種3万本のツバキ園では、日本椿・洋種ツバキなど、色あざやかなツバキが春を彩ります。カメリアハウスでは、貴重な原種・唐椿等を鑑賞することができます。
4月

舞鶴つつじまつり
(4月下旬~5月上旬)
東舞鶴公園で開催されるつつじまつり。
舞鶴市の花でもあるつつじ2万5千本が咲きそろいます。毎年5月4日には、さまざまなイベントも行われます。

瑠璃寺の「しだれ桜」
舞鶴市の指定文化財である、吉田「瑠璃寺」のしだれ桜が美しく花を咲かせます。古木(樹齢400年)と若木(樹齢100年)が織りなす約8mの石垣の上からしだれる姿は迫力満点。田辺城藩主、細川幽斎が幽閉された中院通勝を慰めるために、京都の吉田から桜を移植しました。

与保呂川の千本桜
与保呂川の河口、富士通り付近から当時の海軍鎮守府の施設や艦艇用の水を確保した与保呂水源地迄、桜の並木が川の堤防沿いに延々7kmに渡り、桜約千本植樹され、春になると桜の並木がまるで天の川のように続く様は圧巻です。
「与保呂川の千本桜」と呼ばれ、老若男女揃って桜を見ながらウォーキングを楽しめます。桜はソメイヨシノがほとんどですが、場所によっては、しだれ桜、八重桜も植えられています。
5月

松尾寺・卯月八日の仏舞
(5月8日)
きらびやかな出立の6体の仏たちが雅楽に合わせて舞う「卯月八日大法要」の伝統行事
(国の重要無形文化財)
若狭富士の名で知られる青葉山の中腹に建つ松尾寺は西国三十三所第二十九番札所。国宝普賢延命像(絵画)をはじめ快慶作の阿弥陀如来像など多くの文化財を所蔵し、春秋の各2ヶ月間境内の宝物殿で展示公開される。

田辺城まつり
(5月下旬)
武者行列や芸屋台、伝統芸能などお城のまちらしい催しがいっぱい。
城下町田辺の歴史と文化を今に伝えるイベント。武者行列がまちをねり歩き、立ち並ぶ芸屋台では伝統芸能が披露されるなど、魅力がいっぱいです。
6月

雄島参り
(6月1日)
年に一度、冠島に上陸し、漁民の信仰が厚い老人嶋神社に参拝する行事。
舞鶴では昔から冠島は神の島とされ、「雄島さん」と呼ばれています。

舞鶴自然文化園アジサイまつり
(6月上旬~7月上旬)
梅雨の季節に行われるアジサイ展。約100品種ひとめ10万本ものアジサイが咲き乱れ、アジサイの海が一面に広がります。

朝代神社 夏越の大祓
(6月30日)
家内安全、無病息災を神様に祈る祭りで、日常の生活の中で知らず知らずのうちに犯してしまう罪穢れを祓い清める「大きなお祓い」
この祭りは、古来より半年に1回行われる、日本民族に連綿と伝わる行事です。
人型に息を吹きかけ、身代わりとして罪穢れをうつし、川に流します。
日本人は一年を二期にわけ、半年に一度日々の生活を願みて、罪穢れを水に流し、新しい日々をすがすがしい気持ちで過ごす日本人らしい伝統行事です。
7月

海開き
(7月上旬)
夏の訪れを告げる神崎・竜宮浜・野原の3か所の海水浴場での海開き。日本海沿岸の美しい海を楽しむことができます。

大森神社まつり 大名行列
舞鶴市の彌伽宜神社(大森神社)の例大祭は毎年7月14日15日に行われます。14日には和太鼓や笛の音に合わせて、大名行列が街を練り歩きます。これは1953年9月の台風23号で大きな被害を受けた住民たちが、途絶えていた昔ながらの盛大な奉賛行事として、復興と五穀豊穣を願い、翌年から始めたものです。

みなと舞鶴ちゃったまつり
(7月下旬)
夏の夜を彩る舞鶴のお祭り。舞鶴音頭にのって踊る民謡ながしや舞鶴湾に打ち上がる花火に、会場は大変盛り上がります。

安寿姫塚のキャンドルイルミネーション
(7月下旬)
安寿と厨子王伝説で有名な安寿姫の墓地をキャンドルの灯が幻想的照らします。
季節の花や、特に梅雨時のアジサイは美しく幻想的な世界を作り出します。
8月

城屋の揚松明
(8月14日)
400年以上前から伝わる伝統行事。
高さ16メートルの大松明に小松明を投げ入れ、勇壮な祭りが始まります。
府登録・市指定文化財。

小橋の精霊船
(8月15日)
舞鶴市小橋の海崎寺にまつられた施餓鬼法要の旗やお供物などが積み込まれた精霊舟。
ご先祖さまの御霊を海に送りだします。
府登録文化財。

吉原の万灯籠(まんどろ)
(8月16日)
海神を鎮めるためにと始まった勇壮な盆の火祭り。
伊佐津川の河口にかかる大和橋上手の川中からスタートするという珍しい火祭り。
高さ18m、最大幅5mにもなる万灯籠の炎に、漁業の安全を願います。
府登録文化財。
9月

まいづる魚まつり
(9月第4日曜日)
舞鶴の海の幸を存分に楽しむことができるイベント。
市民参加のせり市、海鮮バーベキュー、寿司卸売りなどが開催されます。
10月

地頭太鼓
毎年10月10日に最も近い日曜日に、氏神様である西飼神社に奉納されます。
地頭は古くは由良川の渡津で、源頼光一行はここから大江山に鬼退治に向かったと言われ、頼光一行の戦勝を祈願して打った太鼓が伝承されています。
丹波地方の「楽太鼓打ち」と同系の太鼓芸で律動豊かにブチを打ちます。戦勝を祈る意味から、ブチは下に向けず、上へ上へと打ち上げます。

大俣太鼓
地頭太鼓同様に西飼神社に奉納される大俣太鼓は源頼光一行の凱旋を祝ったと言われてます。
大江山山系の人たちが祖先から受け継いだ伝統芸能と鬼退治伝説が太鼓という形で定着していることは意義深い。
一人打ちから舞打ち、合い打ち、まわり打ち、「ヤリベス」という師匠格のうちで終わります。

舞鶴赤れんがハーフマラソン
(10月上旬)
赤れんがパークをスタートし、舞鶴湾を臨む海上自衛隊の航空基地や自衛隊岸壁に停泊する見ながら走る舞鶴の魅力を凝縮したハーフマラソンです。
毎年全国から2000名を超えるランナーが参加しています。

神崎の扇踊(府登録 無形民俗文化財)
(10月上旬)
西神崎の湊十二社で、航海の安全などを祈願する祭礼で披露される伝統芸能。扇のひらめきが印象的な踊りであり「扇踊」の名の由来をしのばせる。
太鼓うちは少年の役とされ、東西は袴に烏帽子姿で口上を述べ、太鼓打は長襦袢姿で太鼓を打つ。
11月

吉原の太刀振
(11月3日)
朝代神社の祭礼に、4年に1度奉納される民俗芸能です。
戦国の武将・細川氏が吉原漁民に伝授した武道の型を、今の時代にまで伝えるものです。